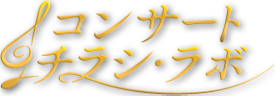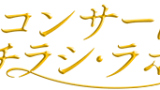クラシック音楽業界用語辞典~オーケストラ奏者が使う専門用語まとめ~
クラシック音楽の世界には独特の専門用語が数多く存在します。オーケストラ奏者たちが日常的に使うこれらの用語を知れば、コンサートやリハーサルの様子がより深く理解できるようになります。
基本用語
【あ行】
アインザッツ
音の出始めの瞬間。アンサンブルではブレスで合図を出したり、指揮棒の動きに合わせて音を出すタイミングを見計らいます。
あおる
最初のテンポより、指揮者や演奏者がどんどん速くしていくこと。
あごあし
出演者やスタッフの宿泊費や交通費を指す業界用語。
あし
管楽器のパートの補助奏者のこと。
アタッカ
楽曲の境目を切れ目なく繋げて演奏すること。楽章間の間を開けずにつなげる指示。
アップ
弦楽器の弓を上げる動作のこと。
アルコ
弓を用いて弾くこと(イタリア語で「弓」の意)。
アロッターヴァ
譜面にある音符より1オクターブ上げて演奏する指示。8vaとも表記。
移調楽器
「ド」の運指で実際には別の音が出る楽器。クラリネット(♭シ)、トランペット(♭シ)など。
インテンポ
表記されているテンポのままで演奏すること。
インペク
楽団全体を取り仕切るリーダー。インスペクターの略。
裏
弦楽器で2人で一つの譜面を見る際、客席から遠い方の奏者。
エキストラ(トラ)
正団員ではないが、特定の公演のために呼ばれる奏者。
オケピ
オーケストラピットの略。舞台の前の一段下がったオーケストラスペース。
オケ譜
オーケストラの譜面。パートがそろった譜面(スコア含む)。
おけら
オーケストラの略称。「オケ」とも。
降り番
管楽器奏者同士で楽曲ごとの入れ替わり。編成によって出演しない出番のこと。
【か行】
かきこみ
譜面に演奏に関する記載をすること。指揮者からの指摘を記入することも含む。
型
弦楽器の編成形態。
カンニングブレス
奏者同士でブレスの場所をバラして分からないようにすること。
替え指
物理的に演奏しづらい運指の場合、他の運指で代用する奏法。
刻む
拍をカウントすること。リズムを正確に刻むこと。
ゲネプロ(GP)
本番通りの衣装と進行で行うリハーサル。ドイツ語のGeneralprobeから。
ゲネラルパウゼ(G.P.)
楽曲中で全楽器が休止となっている部分。
コルレーニョ
弦楽器で弓の木の部分で弦を叩く奏法。
コン・ソルディノ
ミュート(弱音器)をつけて演奏する指示。
コンマス
コンサートマスターの略。第一バイオリンの首席奏者で、指揮者を補佐する役割。
【さ行】
次席
コンマスの隣で演奏する奏者。次のコンマス候補。
下振り
練習で指揮者に変わって指導する指揮者のこと。
初見
譜面を見ながらその場で初めて演奏すること。
スコア
全楽器パートが記載された譜面。
ステマネ
ステージマネージャー。舞台の準備・進行を担う。
ステリハ
ステージリハーサルの略。本番会場でのリハーサル。
スルG
弦楽器でG線だけで弾く指示。
セク練
各セクション(弦楽器、金管楽器など)ごとの練習。
センツァ・ソルディノ
ミュートを外す指示。
ソワレー
夜に行われる演奏会。
【た行】
代奏
本来の奏者に代わって演奏すること。
代振り
代わりに指揮をすること。
ダウン
弦楽器の弓を下げること。
ためる
音符や休符を長めにして間延びさせた演奏表現。
タンギング
管楽器で舌を使って音の区切りを作る奏法。
チューニング
Aの音を基準に音を合わせること。通常オーボエが基準音を出す。
ディヴィジ
同じパート内で分かれて演奏すること。譜面では「div.」と表記。
【な行】
のりうち
移動したその日にゲネプロと本番を行うこと。
乗り番
奏者が演奏する楽曲、出番のこと。
【は行】
パート練
各楽器に分かれて練習すること。
はける
舞台から降りること。
箱
コンサートホール、舞台のこと。
走る
指揮のテンポより速く演奏すること。
外す
意図せず譜面と違う音を出してしまうこと。
はねる
演奏会が終わること。
ピッチ
音程のこと。通常440Hzか442Hzでチューニング。
ピッチカート
弦楽器で指で弦を弾く奏法。
プルト
弦楽器奏者の位置。2人1組で数える単位としても使用。
ブレス
管楽器の息継ぎ。
譜読み
新曲の譜面を理解する作業。
棒
指揮棒のこと。
棒振り
指揮者のこと。
ボーイング
弦楽器の弓の使い方。
【ま行】
マチネー
昼に行われる演奏会。
【や行】
ユニゾン
すべての楽器が同じ音程で演奏すること。
楽曲関連用語
アウフタクト
弱拍から始まる音楽。指揮の上げ動作から始まる。
アリア
オペラなどで歌われる抒情的な独唱曲。
アルペジオ
分散和音。和音を分解して演奏すること。
アンサンブル
複数奏者による演奏。また演奏の調和を指す。
アンダンテ
「歩くように」の中程度のテンポ。
インテルメッツォ
間奏曲。オペラの幕間などに演奏される。
エチュード
練習曲。技巧習得を目的とした楽曲。
エレジー
悲歌。哀悼の意を表す楽曲。
カデンツァ
協奏曲で独奏者が即興的に演奏する部分。
カノン
輪唱のように旋律を追いかける形式。
カンタービレ
「歌うように」演奏する指示。
協奏曲
独奏楽器とオーケストラのための楽曲形式。
交響曲
管弦楽のためのソナタ。多楽章形式。
交響詩
文学的・絵画的内容を表す管弦楽曲。
ソナタ
器楽独奏または二重奏のための楽曲形式。
ロンド形式
主題が繰り返し現れる楽曲形式。
演奏会用語
カーテンコール
演奏終了後の出演者への拍手と挨拶。
クロクロ/シロクロ
女性奏者の衣装(上黒下黒/上白下黒)。
板付き
演奏開始時から舞台上にいる状態。
楽器関連用語
ライブラリアン
楽譜を管理する人。
リード
木管楽器の振動部品。
マウスピース
管楽器の吹き口。
ミュート
弱音器。楽器の音量を抑える装置。
略称
ドボハチ
ドヴォルザークの交響曲第8番。
ブライチ
ブラームスの交響曲第1番。
ベトシチ
ベートーヴェンの交響曲第7番。
マラゴ
マーラーの交響曲第5番。
モツレク
モーツァルトのレクイエム。
メンコン
メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲。
おわりに
クラシック音楽の世界は長い歴史の中で培われた独特の用語が豊富です。これらの用語を知ることで、演奏会やリハーサルの様子がより鮮明にイメージできるようになるでしょう。オーケストラの舞台裏を覗くような気分で、ぜひこれらの用語を楽しんでください。
※この記事はクラシック音楽業界で一般的に使用されている用語をまとめたものです。団体や地域によって用法が異なる場合があります。